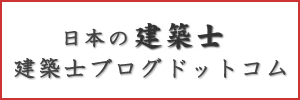不動産物権変動と登記⑦
記事投稿日2014年09月29日月曜日
投稿者:一般社団法人エースマンション管理士協会 カテゴリー: General
8 通謀虚偽表示と登記
① 通謀虚偽表示とは、契約の当事者ABが、通謀して真意と異なる意思
表示(虚偽の意思表示)をすることである(Aが債権者の差押えを免れる
ため、財産(土地・建物等)をBに売却したように財産を隠す目的で売買
契約を装う場合が典型例である)。
通謀虚偽表示は、当事者間に契約を締結する意思が欠けているので
あるから、無効とされている(民法94条1項)。したがって、Aの債権者は、
当該土地をAのものとして差し押さえることができる。
この無効は、善意の第三者に対抗できない(民法94条2項)。つまり、
ABの当事者間では売買契約は無効であり、何らの効果も生じないが、
AB間の事情を知らずに(善意)、CがBより当該土地を買受けたり、賃
借したり、抵当権を設定したり、差押えをしたりした場合に、Aは、Cに
Bとの契約の無効を主張して、当該土地の所有権を主張して返還せよ
とか、賃借権や抵当権は無効だとか、差押さえは無効だとか言えない
ということである。つまり、AB間が有効な契約であると信じてBと取引
をしたCを保護しようとするものである。虚偽表示をした者より、善意の
第三者を保護する必要があるからである。したがって、この場合には、
Aの債権者も、善意の第三者に対しては差押えはできなくなる。第三
者は善意であればよく、過失の有無を問わない。また、第三者は登記
をしていなくてもよい(判例)。
また、善意の第三者Cからさらに譲り受けた者D(転得者)が悪意で
あっても、AはDに対しても対抗できない。一度善意者が介在すると、
以後はその地位を承継するからである。
直接の第三者Cが悪意でも、転得者Dが善意であれば、AはDには
対抗できない。
Aが善意の第三者C・Dに対抗できないときでも、Aは、Bに対しては
無効の主張ができ、Bの責任を追及できる。
心裡留保が例外的に無効とされる場合に(民法93条ただし書)、94
条2項を類推適用して、善意の第三者に対抗できないと解されている。
判例⇒ 通謀虚偽表示とは言えないが、Aが建物を新築したが、Bに無
断でB名義の所有権保存登記をしていたところ、Bが勝手に自己
の所有物としてCに売却した場合、Cが善意であれば、通謀虚偽
表示の規定(民法94条2項)を類推適用して、Aは、Cに当該建物
の所有権を対抗できないとした判例がある。
AB間には通謀や虚偽の売買もないが、虚偽の外形を作ったA
よりも、これを信頼したCを保護すべきだからである。
判例⇒ Aの所有地をBが勝手に自己名義の登記をしているのをAが
知ったが、すぐに登記を回復することなく放置していたところ、善
意のCがBから当該土地を買受けた場合、民法94条2項を類推
適用して、Aは、Cに当該土地の所有権を対抗できないとした判
例がある。
この事例では、Aが積極的に虚偽の事実を作り上げているわ
けではないが、自分の土地について登記が第三者名義になって
いることを知りながらこれを放置することは、自ら虚偽の事実を
作り上げていることと変わりがないと判断されたのである。
以上と異なり、A所有土地・建物について、Bが勝手に自己の所有物
として登記をして、Aが知らない間に、BがCに売却した場合、Cが善意
であっても、Aは当該土地・建物の所有権をCに対抗できる。この場合、
Aに何らの帰責事由がないからである。不動産については単に登記を
信頼しただけでCが保護されるものではないことに注意すること。
ちなみに、動産については、相手方の占有を信頼して取引に入った
場合、動産の所有権を取得できるとする、即時取得(善意取得)の制度
があるが(民法192条)、この点については、最初の方でみたように、
不動産の登記については、公信力がなく、動産の占有については公信
力が認められているとして述べている。
② AB間のA所有土地の売買契約が通謀虚偽表示である場合、C
が善意でBから当該土地を買受けたときは、Cが善意であれば、C
は登記をしなくても、Aに所有権を対抗できると言ったが、Cは、A
から当該土地を買受けたDに対しては、登記をしなければ対抗で
きない(判例)ことに注意すること。もちろん、Dも登記をしなければ、
善意のCには対抗できない。つまり、この場合、A所有土地がA→
B→Cと譲渡され(AB間の無効を善意のCに対抗できないという
ことは、Cからみれば、AB間は有効となるという意味である。)、
さらにA→Dに二重に譲渡された場合と同様に考えて、CとDは対
抗関係に立つと見るのである(民法177条)。平成12年度【問4】
肢4。
- 記事投稿者情報 ≫ 一般社団法人エースマンション管理士協会
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫